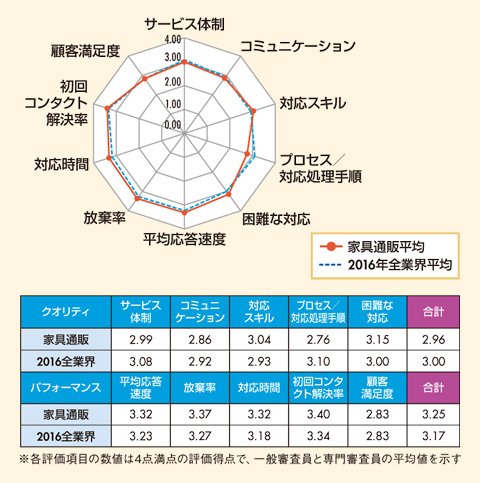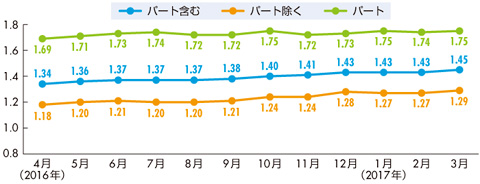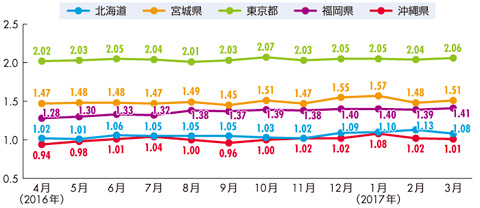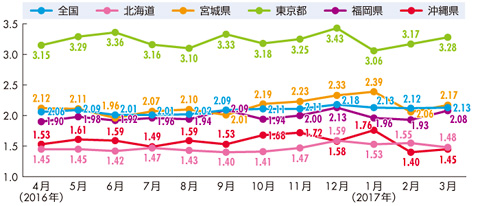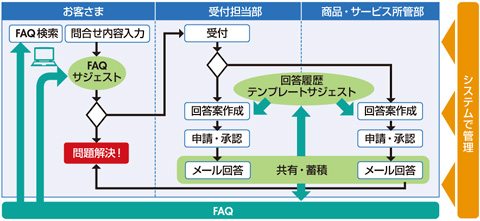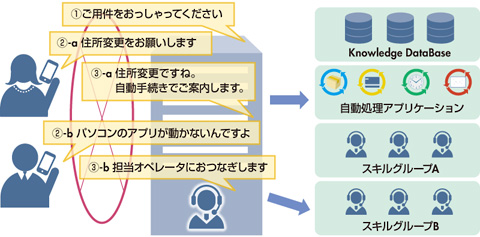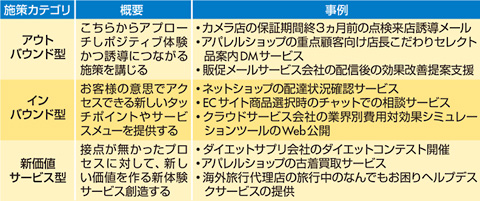エンジニアの妥協は現場の“不便”を招く
対話でつくる「5年後も使えるシステム」
NEC
スマートネットワーク事業部
カスタマフロントソリューション事業グループ
マネージャー
増田 一郎 氏
“使えるコンタクトセンターシステム”には、ユーザー企業(現場)とシステムエンジニアとの信頼関係が必要だ。NECのセンター提案・構築の一翼を担う増田一郎マネージャーは、「ユーザー企業の『こんなことがしたい』をシステムに落とし込むには対話が最も重要」と強調する。
──カスタマフロントソリューション事業グループは、顧客接点に関わるソリューションの提案、構築専門の部隊と聞いています。
増田 開発、営業、私が所属するシステムエンジニア(SE)の3部門から、コンタクトセンターや店舗、Webなど、あらゆる顧客接点に関わるソリューションの担当部隊を集約しています。
私は入社から16年間、コンタクトセンター構築を担当してきましたが、現在の受注は案件ベースで過去最大規模と言えます。1件1件、丁寧かつ迅速に応えるには、提案から運用開始、サポートまでワンストップで提供できる体制が不可欠でした。
──1件あたりの人的資源や時間は限られるなかで、丁寧・迅速を実現するために工夫していることはありますか。
増田 手戻りがないよう、受注が決まった段階から移行直前まで、出来る限りお客様(ユーザー企業)との対話時間を設け、合意形成を図るようにしています。とくに、システム移行直前のオペレータやSVの操作習熟期間にいただく要望には耳を傾けるようにしています。システムは、運用現場にとっては5年、6年と毎日のように利用するものです。納期間近の細かい要望は、つい「どうにか運用で回避してくれませんか」と言ってしまいがちですが、そこでの妥協は現場にとって“毎日の不便”を生んでしまいます。
どこまで現場の方々と一緒にユーザー体験を追求できるか。そこでSEとしての「価値」が決まると考えています。構築チームを預かるマネージャーとして、メンバーとも「SEのあり方」を共有しています。
──コールセンターは「特殊性の強い組織」と言われています。ユーザー体験の追求は相当難しいのでは。
増田 だからこそ、お客様との合意形成を図ることが何よりも重要です。対話によって「こうしてほしい」という要望を溜め込まずに言える関係にまで醸成できればスムーズに進められます。結果的に、構築期間の短縮にも繋がります。現場の習熟と細かな使用感の調整に充てる時間も創出することができ、ベンダーと現場双方が納得できる完成度まで高めることができます。
──すべての場面において、現場との対話が重要なのですね。
増田 お客様のビジョンをシステムに具体的に落とし込むことが仕事ですから、対話ナシに良いシステムは構築できません。近年は、「AI(人工知能)で何でも解決」のような抽象度の高い案件も散見されます。これからは、本当にAIで解決すべき業務課題かどうかも含めて「具体的なシステム像」を一緒に考える必要がありそうですので、対話重視のスタンスをさらに強めることになると思います。